心不全とは
心不全とは、簡単にいうと心臓が弱って全身に十分な血液を送り出せなくなった状態のことです。心臓のポンプとしての働きが低下し、体に酸素や栄養が行き渡りにくくなるため、息切れやむくみなどさまざまな症状があらわれます。安静にしていれば症状が落ち着いていても、少し無理をすると息苦しさが出るといったように、良くなったり悪くなったりを繰り返しながら徐々に進行するのも心不全の特徴です。
では、具体的にどのような症状が出るのでしょうか。心不全の主な症状には、坂道や階段での息切れ、靴下の跡が残るほどの足のむくみ、身体のだるさなどがあります。症状が進行すると、横になると息苦しくて眠れないこともあります。
なぜ心不全になるのか? 主な原因として、長年にわたる高血圧(血圧が高い状態)が挙げられます。高血圧が続くと心臓に負担がかかり、次第にポンプ機能が弱ってしまいます。また、一度起こした心筋梗塞の後遺症で心臓の働きが低下することがあります。そのほか、心臓の弁の異常(弁膜症)や不整脈などの心臓病、さらには加齢による心臓の筋肉の衰えも心不全の原因となります。
心不全は特に高齢の方に多い病気です。65歳以上では約10人に1人が心不全を抱えているとも言われます。今後心不全の患者さんはさらに増えると予想されています。心不全になった場合、完治することは難しいですが、症状とうまく付き合いながら長くお付き合いしていく病気となります。ただし、適切な治療を続けることで症状を和らげたり進行を遅らせたりすることが可能です。日々の体調管理をしっかり行えば、悪化を防いで普段と変わらない生活を送ることもできます。次に、心不全と診断された場合にどのような治療や生活管理が必要になるのか、基本的なポイントを見ていきましょう。
心不全の治療の基本:薬・食事・運動・リハビリテーション
心不全と診断された場合、薬の治療や生活習慣の改善によって症状をコントロールし、悪化を防ぐことが目標になります。治療において特に次のようなポイントが重要です。
- お薬をきちんと飲むこと: 心不全の治療では、心臓の負担を減らしたり余分な水分を体から排出したりするために、複数の種類の薬が処方されます。処方されたお薬は医師の指示通りに毎日欠かさず飲むことが何より大切です。体調が良いからと自己判断で中止したり、飲み忘れが続いたりすると、症状が再び悪化してしまう恐れがあります。飲み忘れを防ぐために、朝昼夕のお薬を小分けにしておけるケースを使ったり、カレンダーにチェックを入れたりといった工夫も有効です。お薬の数が多く管理が大変なときは、訪問看護師や薬剤師に相談し、負担の少ない管理方法を教えてもらいましょう。
- 塩分と水分の管理: 食事面では塩分を控えることが特に重要です。塩分の摂りすぎは体内に水分を溜め込み、心臓に大きな負担をかけてしまいます。なるべく薄味に慣れ、醤油や味噌などの濃い調味料は控えめに使い、漬物やインスタント食品など塩分の多い食品もできるだけ控えましょう。水分の摂りすぎにも注意しましょう。症状が重い場合は医師から1日の水分量を制限されることもあります。喉が渇いても一度に大量に飲まないようにし、むくみが強いときは水分を控えめにしましょう。毎朝体重計に乗って、前日より急に増えていないか確認する習慣も大切です。体重増加は水分が溜まっているサインなので、早めに気づけば悪化を防げます。
- 無理のない運動とリハビリ: 症状が安定しているときは、適度に体を動かすことも治療の一部です。安静にしすぎると筋力が落ち、日常の動作が難しくなり心臓への負担も増えます。医師と相談のうえ、散歩や軽い体操など無理のない運動を続けてみましょう。適度な運動を続けると心臓だけでなく足腰の筋肉も強くなり、息切れしにくい体づくりにつながります。加えて、体を動かすことは良い気分転換となり、ストレスの解消にも役立ちます。ただし体調が優れない日は無理をせず、安静に休むことも忘れないようにしてください。
- その他の生活習慣: お薬・食事・運動以外では、喫煙と飲酒の習慣を見直すことが重要です。タバコは心臓に負担をかけるため禁煙が基本です。お酒も大量に飲むと症状を悪化させる原因になるため、医師から飲酒制限や禁酒を指示されている場合は必ず守りましょう。さらに、十分な休養と睡眠をとり、疲労やストレスを溜めないようにすることも大切です。また、無理のない範囲で趣味や友人との交流を楽しむことも心のリフレッシュにつながります。
在宅医療と訪問看護の役割:再入院予防から看取りまで
病院での治療を終えて自宅に戻った後、在宅療養ではご本人やご家族が不安に感じることも多いでしょう。そうしたときは、定期的に訪問する訪問看護師が体調管理や生活面のサポートを行い、安心して暮らせるようお手伝いします。
訪問看護師の大きな役割の一つに、心不全の悪化予防があります。心不全は一度安定しても、ちょっとしたきっかけで症状が急に悪化し、再び入院が必要になることが少なくありません。訪問看護師はご自宅での様子を細かく観察し、例えば「足のむくみがいつもより強い」といった悪化のサインを早めにキャッチします。そして主治医と連携して早期の対処につなげ、重症化や再入院を未然に防ぎます。
また、訪問看護では服薬管理の支援も重要な役割です。心不全の治療では複数の薬を用いるため、「つい飲み忘れてしまう」「飲んだかどうか分からなくなる」といったことが起こりがちです。訪問看護師がお薬カレンダーの活用方法をアドバイスしたり、1回分ずつを一袋にまとめる工夫を医師や薬剤師に相談したりして、患者さんが確実に薬を飲み続けられるようサポートします。また、副作用が疑われる症状があれば速やかに医師に報告し、薬の調整を含めた対応を検討します。
さらに、自宅でのリハビリテーション支援も欠かせません。動くと息苦しくなるため活動量が減ってしまいがちですが、訪問看護師や理学療法士がご自宅で一緒に軽い体操や歩行練習を行うことで、筋力の低下を防ぎ、心肺機能の維持をお手伝いします。継続的なリハビリは息切れしにくい体づくりにつながり、日常生活の自立度を高めてくれます。リハビリの内容は一人ひとりの体調に合わせて調整されるため、無理なく続けることができます。
そして、病状が進んで治療が難しくなった場合には看取りの支援を行うことも訪問看護の大切な役割です。「できれば住み慣れた自宅で最期を迎えたい」という患者さんやご家族の希望を尊重し、主治医と連携しながら症状緩和や介護面のサポートを提供します。ご家族には、死が近づくと現れる症状について事前に説明し、心のケアにも努めます。24時間いつでも相談や緊急訪問ができる体制を整えており、「何かあってもすぐに専門家に頼れる」という安心感につながっています。
心不全の患者さんが住み慣れた地域やご自宅で自分らしく生活を続けるためには、医療と介護のチームが一丸となって支えることが大切です。訪問看護はその中心的な役割を担い、ご本人とご家族に寄り添いながら、病気との付き合いを最後まで支えていきます。
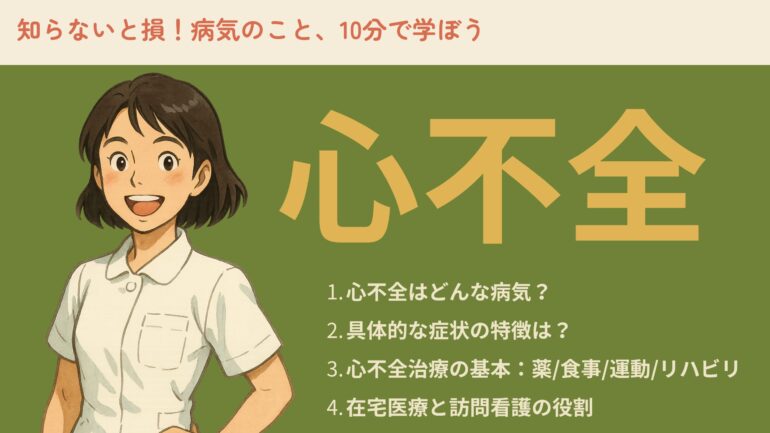
「心不全とはどんな病気でしょうか?」へのコメント
コメントはありません